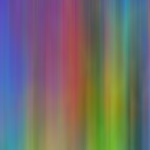ブラニュー株式会社は東京の港区六本木に本社を置き、建設業界向けのDXプラットフォームを展開している企業です。
建設業の業務効率をアップさせるべく、クラウド型のワークマネジメントツールCAREECONを開発、提供を行っているのが特徴です。
50年間生産性が上がっていないといわれる建設業にピントを合わせ、産業構造を変えるべくデジタル技術で挑戦しているのがこの企業です。
建設業は人材不足に直面していますが、若者が誇りを持って働くようなイメージと結びついていないのがネックです。
つまり、若者が興味を持ったり前向きに働こうとする状況が生まれておらず、それが人材不足に拍車を掛けているわけです。
目次
建設業の産業構造や情報流通の歪をテクノロジーの力で変える
建設業に従事する人達の高齢化も無視できませんし、今後技術が継承されていかなければ、いずれ技術は廃れて日本の建築物の質は落ちてしまうでしょう。
ブラニュー株式会社は危機感を覚え、現在建設業が抱えている問題にメスを入れて、産業構造や情報流通の歪をテクノロジーの力で変えようとしています。
建設業というと、給与が上がらず頑張っても稼げないイメージがありますが、これも産業構造の問題によるところが大きいです。
いわゆる下請けの孫請といった構造が末端にもたらされるお金を減らし、得られる報酬が減ってしまうのが問題です。
代表を務めるCEOは小さい頃から建設業を見てきた人物で、抱えている問題であったり、変革の必要性を理解しています。
デジタル技術でできることはないか、そう考えた結論の1つがDXで、テクノロジーによる変革です。
業界全体で変革を行うデジタルトランスフォーメーション
着目したのは中小企業のスモールビジネスで、業界全体で変革を行うデジタルトランスフォーメーションです。
日本の建設業は殆どが中小企業で、建設によって文字通り日本社会を支えてきた存在です。
ところが、産業構造の問題で生産性が上がらず、若者にとって魅力的に見えない産業になってしまったのも事実です。
ブラニュー株式会社は若者が働きたくなるような産業にする為に、中小企業を変革しようとしています。
具体的には下請けなどではなく直接仕事が得られるようにしたり、価値を生み出して提供できるようにすることです。
いつまでも多重下請け構造に甘んじていては何も変わりませんし、非効率な慣習を続けていると人手不足を前に立ち行かなくなるでしょう。
ブラニュー株式会社のCAREECON
ブラニュー株式会社のCAREECONは、建設業向けのオンラインマッチングプラットフォームで、紹介による仕事の獲得以外の受発注ルートを確立するのに役立ちます。
インターネットを使うことで仕事に出合えますし、高度なマッチングによって安定的に仕事が得られるようになります。
これがまさにデジタルトランスフォーメーションをもたらす取り組みの1つで、CAREECON自体もアップデートを重ねながら業界を少しずつ変革させています。
主要な事業の柱にはもう1つ、デジタルマーケティングがあります。
デジタルマーケティングでは経営課題の解決に不可欠な、意思決定をサポートする取り組みを行っています。
ポイントはデータの活用で、データを元に企業活動のデザインであったり、デジタル領域のパートナーとしてビジネスの成長の貢献、寄与しているのがブラニュー株式会社です。
CAREECONforWORK施工管理
CAREECONforWORK施工管理は、名前の通り施工管理担当者向けのサービスで、データ管理や共有にコミュニケーションの部分で負担軽減を図るものです。
これらの課題を解決することによって、施工管理業務の効率化を図っているのがCAREECONforWORK施工管理というわけです。
クラウドベースの施工管理ツールですから、インターネット環境があればどこからでもアクセスできますし、何より導入のハードルが低いのが魅力的です。
CAREECONSitesは本業に集中する為に、手間の掛かるWebサイト管理をノーコードで実現するプロダクトです。
スモールビジネスが苦手とするバックヤード業務、マーケティングを自動化するプロダクトが開発されているので、CAREECONSitesからも目が離せないです。
まとめ
ブラニュー株式会社は2009年の設立以来、約100名規模の従業員が日々、建設業の方を向いてデジタルトランスフォーメーション事業を展開しています。
その注目度は高く提携したり、パートナー企業になる会社も多く、業界全体にデジタルトランスフォーメーションの貢献をしていることが分かります。
変化を恐れない社風で、一歩を踏み出す勇気がありますから、現在のような革新に繋がる取り組みが行えているといえます。
社内公募制度や新規事業をスタートアップしやすい環境、インセンティブ制度やストックオプション制度などを採用している企業なので、勇気を出して大胆な取り組みができます。
自社が成長するシステムを確立していますから、成長を続けながら建設業に貢献できますし、業界を支える裏方として今後も注目を集め続けると思われます。