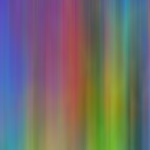エステティック業界のパイオニアとして、46年以上にわたり日本の美容文化をリードしてきた「たかの友梨ビューティクリニック」。
全国75店舗、のべ2300万人以上のお客様に愛され続けるこのブランドの強さは、どこにあるのだろうか。
美容業界を30年以上取材してきた私、森田香代子が、たかの友梨で働く女性たちへの取材を通じて見えてきたのは、単なる技術力や接客スキルを超えた、深い信念と情熱の存在だった。
「自分の名前にかけて責任を持ってお客様をケアし続ける」——創業者・たかの友梨のこの言葉は、今も現場で働く一人ひとりの心に息づいている。
本稿では、カウンセラー、エステティシャン、マネージャーという異なる立場で活躍する女性たちの声を通じて、”美の職人たち”の素顔と、彼女たちが体現する「たかのイズム」の本質に迫りたい。
ブランドの内側にある理念と文化
“美の殿堂”たかの友梨、そのブランド力の源泉とは
私がたかの友梨ビューティクリニックを初めて取材したのは、今から20年以上前のことだ。
当時から感じていたのは、このブランドが持つ独特の存在感だった。
「エステといえば、たかの友梨」——この認知度の高さは、単なるマーケティングの成果ではない。
取材を重ねるうちに見えてきたのは、徹底した直営店経営によるクオリティコントロールの実現だった。
「全店舗が本社直営というのは、業界では珍しいんです」と、ある店長は語ってくれた。
「フランチャイズにすれば早く拡大できますが、それでは技術やサービスの質を保てない。たかの友梨という名前を背負う以上、すべてのお客様に同じレベルのサービスを提供する責任があるんです」
この言葉に、ブランドの本質が凝縮されている。
社内に息づく「美は信念」の哲学
「愛といたわりの精神」——これが、たかの友梨ビューティクリニックの経営理念だ。
しかし、理念を掲げることと、それを現場で実践することは別物である。
私が注目したのは、この理念がどのように日々の業務に落とし込まれているかという点だった。
実は、この理念の背景には創業者・たかの友梨自身の複雑な生い立ちがある。
3歳で養子に出され、苦労を重ねた彼女だからこそ、人の痛みを理解し、誰かを支えることの大切さを知っている。
その経験が、たかの友梨が子供たちへ向けて行うボランティア活動にも繋がっており、児童養護施設「鐘の鳴る丘少年の家」の後援会長として、長年にわたり支援を続けている。
新人研修の現場を見学させていただいた際、印象的だったのは技術指導の前に行われる「心の教育」だった。
「エステティック技術だけでなく、皮膚医学、生理解剖学、東洋医学、栄養学、消毒法、心理学、マナーなどの基礎教育を必須化しています」と、教育担当者は説明する。
特に心理学やマナーに時間を割いているのは、「真のエステティシャンは、高度な技術だけではなく『愛といたわり』の心を持ち、お客様に癒しや深いやすらぎを感じていただける”美のセラピスト”でなければならない」という信念からだという。
女性スタッフが語る「たかのイズム」とは何か?
「たかのイズムって何ですか?」
私がこの質問を投げかけると、スタッフたちは一様に微笑みながら、それぞれの言葉で答えてくれた。
「お客様一人ひとりと真剣に向き合うこと」
「技術を磨き続ける姿勢」
「仲間を大切にする心」
興味深いのは、誰一人として同じ答えを返さなかったことだ。
それでいて、すべての答えに共通するのは「人を大切にする」という軸だった。
ベテランエステティシャンの一人は、こう語った。
「たかの友梨は『女性の、女性による、女性のための企業』を掲げています。これは単に女性が多い職場という意味ではなく、女性の気持ちを理解し、女性の幸せを本気で考える企業だということ。それが私たちの誇りです」
現場で働く女性たちのリアルな声
カウンセラー:一人ひとりの心に寄り添う技術
「カウンセラーの仕事は、お客様の”なりたい自分”を一緒に見つけることです」
入社5年目のカウンセラー、山田美香さん(仮名)は、そう切り出した。
彼女の机の上には、びっしりと書き込まれたカルテファイルが並んでいる。
「お客様のお悩みは十人十色。肌の状態だけでなく、ライフスタイル、ストレスの状況、今までのケア歴…すべてを把握した上で、最適なプランをご提案します」
印象的だったのは、彼女がカルテに書き込んでいた内容の細かさだ。
「先月お子さんが受験だったから、今月は少しリラックスできるメニューを」
「転職されたばかりなので、疲れを癒すケアを中心に」
こうした個人的な情報まで把握し、それをケアに反映させる。
これこそが「一人ひとりの心に寄り添う技術」の本質なのだろう。
エステティシャン:技術と信頼を育てる日々のルーティン
「毎朝、開店前の1時間は技術練習の時間です」
エステティシャン歴10年の佐藤陽子さん(仮名)が見せてくれたのは、練習用のマネキンだった。
「他では決して真似のできない、たかの友梨直伝のハンド技術。これは一生ものの財産です」
彼女の手の動きを見ていると、まるで楽器を奏でるような優雅さがある。
「世界40ヵ国以上の技術を、日本人の肌に合うようにアレンジしたオリジナル技術。これを身につけるには、日々の練習が欠かせません」
しかし、技術だけではお客様の信頼は得られないと、佐藤さんは続ける。
「あるお客様から『ありがとうございます』という言葉に心がこもっていないと指摘されたことがあります。それ以来、言葉一つひとつに感謝の気持ちを込めるよう心がけています」
こうした小さな気づきの積み重ねが、プロフェッショナルを作り上げていく。
店長・マネージャー:組織を動かす”美の司令塔”たち
「店長の仕事は、スタッフ一人ひとりが輝ける環境を作ること」
そう語るのは、都内の主要店舗で店長を務める高橋智子さん(仮名)だ。
彼女のもとには、20代の新人から40代のベテランまで、様々な年代のスタッフが働いている。
「どのサロンも雰囲気が明るく、やさしい笑顔にあふれている——これがたかの友梨の自慢です。でも、これは自然にできることではありません」
高橋さんが重視しているのは、スタッフ同士のコミュニケーションだ。
「お客様を笑顔にするには、まず私たち自身が笑顔でいること。そのために、朝礼では必ず全員で今日の目標を共有し、終礼では良かったことを分かち合います」
マネジメントで特に気を配っているのは、技術の伝承だという。
「ベテランの技術を若手に伝える。これは口で説明するだけでは不十分。実際に見て、触って、体で覚えてもらう。そのための時間を必ず確保しています」
中堅から若手への技術継承と人材育成
私が特に感銘を受けたのは、技術継承のシステムだった。
「お世話係制度」と呼ばれるこの仕組みは、新人一人に必ず先輩が付き、マンツーマンで指導するというものだ。
「技術だけでなく、接客の心構え、お客様との向き合い方まで、すべてを伝えます」と、お世話係を務める中堅スタッフは語る。
「私も先輩から受け継いだものを、次の世代に伝える責任があります。これが、たかの友梨の技術と精神が46年以上続いている理由だと思います」
“美の仕掛け”の舞台裏
接客メソッドと心理的アプローチの工夫
たかの友梨の接客には、独特のメソッドがある。
それは「五感に訴える」アプローチだ。
「サロンに入った瞬間から、お客様の五感すべてに働きかけます」
教育担当者が説明してくれた内容は、実に緻密だった。
視覚——エレガントで上質なインテリア。
聴覚——心地よいBGMと、スタッフの穏やかな声。
嗅覚——アロマの香り。
触覚——ふかふかのタオルと、エステティシャンの温かい手。
味覚——施術後のハーブティー。
「これらすべてが調和して、初めて『癒しの空間』が生まれます」
リピーターを育てる仕組みとその戦略
「リピート率の高さが、たかの友梨の強みです」
マーケティング担当者のこの言葉を裏付けるように、取材中も多くの常連客の姿を目にした。
「10年、20年と通い続けてくださるお客様も珍しくありません」
その秘訣を尋ねると、意外な答えが返ってきた。
「特別なことはしていません。ただ、お客様一人ひとりのことを本当に大切に思い、その気持ちを行動で示すだけです」
具体的には、カルテの徹底管理、定期的なフォローコール、季節に応じたケアの提案など。
しかし、最も重要なのは「お客様の変化に気づくこと」だという。
「髪型が変わった、表情が明るくなった、少し疲れているように見える——こうした変化に気づき、声をかける。それがお客様との信頼関係を深めます」
スタッフの美意識を高める教育制度の全貌
「美容のプロとして、まず自分自身が美しくあること」
この考えのもと、たかの友梨では充実した教育制度を設けている。
新人研修、正社員研修、ステップ研修と、段階的な研修システム。
さらに、外部講師を招いての特別講習会も定期的に開催される。
「技術研修だけでなく、メイクアップ講座、マナー研修、さらには栄養学まで。トータルビューティーを提供するには、幅広い知識が必要です」
研修担当者が見せてくれた年間スケジュールには、びっしりと研修予定が書き込まれていた。
「学ぶことに終わりはありません。だからこそ、この仕事は面白いんです」
森田香代子が見た「たかの友梨」の魅力
実体験から読み解く”ファン心を育てる”現場力
私自身、30代後半でたかの友梨のサロンに通い始めた一人だ。
当時の私は、仕事のストレスと年齢による肌の変化に悩んでいた。
「森田さん、最近お仕事が忙しそうですね。肩に力が入っていますよ」
初回のカウンセリングで、担当者にそう言われたことを今でも覚えている。
肌の悩みを相談しに来たはずが、いつの間にか仕事の愚痴まで聞いてもらっていた。
「エステは、体と心の両方をケアする場所なんです」
その言葉通り、施術を受けるたびに、肌だけでなく心まで軽くなっていく感覚があった。
これこそが「ファン心を育てる」秘訣なのだろう。
技術力はもちろん重要だ。
しかし、それ以上に「この人になら任せられる」という信頼関係。
「また来たい」と思わせる温かい雰囲気。
これらすべてが揃って初めて、真のファンが生まれる。
他社エステとの違いとは?ベテラン目線の比較考察
30年以上、様々なエステサロンを取材してきた私から見て、たかの友梨の最大の特徴は「一貫性」だ。
創業から46年以上、ぶれることなく「愛といたわりの精神」を貫いている。
他社では、トレンドに合わせてコンセプトを変えることも多い。
しかし、たかの友梨は違う。
「時代に合わせて技術は進化させる。でも、根本の精神は変えない」
この姿勢が、長期的な信頼につながっている。
また、スタッフ教育の徹底ぶりも他社とは一線を画す。
「3段階の研修とサロン実地研修を重ね、当社規定の技術検定を取得した者のみが、エステティシャンとして活躍できる」
この厳しい基準が、サービスの質を保証している。
美容業界全体への示唆:たかの友梨が教える”継続”の哲学
美容業界は移り変わりが激しい。
新しいサロンが次々とオープンし、そして消えていく。
そんな中で、たかの友梨が46年以上続いている理由は何か。
取材を通じて見えてきたのは、「継続」への強いこだわりだった。
「お客様との関係は、一回限りではありません。10年、20年と続く関係を築くことが、私たちの目標です」
ある店長の言葉が印象的だった。
この「継続」の哲学は、顧客との関係だけでなく、スタッフの育成、技術の伝承、そして社会貢献活動にまで及んでいる。
毎年恒例の「母の日エステボランティア」、児童養護施設への支援、災害時のエステボランティアなど。
これらの活動を「継続」することで、企業としての信頼を積み重ねている。
まとめ
取材を終えて、私の手元には膨大なメモが残った。
そこに書かれているのは、単なる企業情報ではない。
一人ひとりの女性たちの、仕事への情熱と誇りの記録だ。
「たかの友梨で働くということは、美のプロフェッショナルとして生きること」
あるエステティシャンの言葉が、すべてを物語っている。
彼女たちは単に技術を売っているのではない。
「愛といたわりの精神」を形にし、それをお客様に届けている。
その使命感と誇りが、たかの友梨というブランドを支えている。
美容業界で働くことの意義。
それは、人を美しくすることで、その人の人生を豊かにすること。
外見の美しさは、内面の自信につながる。
自信は、その人の生き方を変える力を持つ。
「美に向き合うこと」は、まさに「生き方に向き合うこと」なのだ。
たかの友梨で働く女性たちは、その重要性を理解し、日々実践している。
だからこそ、彼女たちの仕事には深みがあり、説得力がある。
これからも、たかの友梨の「美の職人たち」は、その情熱と信念を持って、多くの女性たちの美と幸せを支え続けるだろう。
そして、その姿は、美容業界全体にとっての道標となるに違いない。